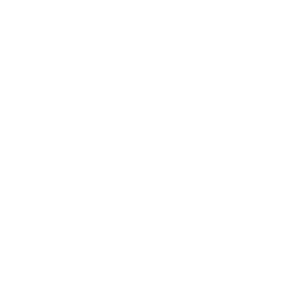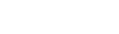その時その時の、茶葉のポテンシャルを引き出す。
秋林:ごとう製茶の紅茶の特徴や長所は何ですか?
後藤:全般的には渋みが少ない紅茶を、香り重視でつくっているところです
味と香りのバランスで、味が重い紅茶は、香りが味の方に引っ張られてしまって香りを感じにくくなります。味や渋みを抜くと、華やかな香りの方を感じやすくなる。
ただ、それは長所でもあるし、短所でもあるかもしれません。好み次第ですよね。香り重視より、重い味を好む方もいるので。
秋林:最初につくった時からこういう感じの、香り重視の紅茶でしたか?
後藤:目指していたのは、最初から香り重視の紅茶でした。
実は最初につくった紅茶が、一番出来がよかったんです。2013年前半はまだ、お茶を生業とするか決断できずにいたのですが、そこでめちゃくちゃいいものができでしまった。当時は「いい」という認識もなく、初めてつくって、「こういう風になるんだ」という感じだったんですが。その紅茶は味のバランスもすごくよかった。この紅茶の出来が、お茶づくりと向き合う覚悟を決める要因のひとつになりました。
秋林:確かに、僕も最初につくったお茶がすごくおいしかったんですよ。難しいことを考えないのがよかったのかな。
後藤:かもしれない(笑)
秋林:ただ、何かしらロジカルに残さないといけないところもあって、データは必要かなと思ってやってるんですけど、結果的にあんまりいい方向にいかないことも……
後藤::どんどん悪くなってくる(笑)ありますね。結果、僕は最近はほとんどメモを書いていないです。

秋林:後藤さんが目指すお茶は、最終的には味覚なども超越したものだと思うのですが、あえて「渋みが少なく、香り高いもの」を目指したのはなぜですか?
後藤:まず、テイスティングするのは自分だから、自分の好みに寄りますよね。僕は渋みが好きではなかった。それから、香り重視の紅茶を最初に飲んだ時に、「これはすごい!」と思った。
秋林:どちらの紅茶ですか。
後藤:ダージリンです。本当に、マスカットの香りがした。
秋林:特徴的ですよねやっぱりダージリンは。
後藤:家を手伝い始めた2012年のシーズンの終わり頃、インドにいく機会に恵まれました。その際にダージリンで飲んだ紅茶です。乗用車で、ミャンマーとかネパール、中国の国境沿いをぐるっとまわり、道を走りながら見つけた茶園で、通訳の方を通してお願いして、見学させて貰いました。
秋林:アポなしですか!すごいですね。その時のダージリンティーを指標や目標に?
後藤:インドと日本では環境など何もかもが違いすぎて、結局、日本の紅茶には日本の紅茶の香りがあるだろうから、その中でいいものを探そう、日本にあう最適な条件を自分でみつける以外にはないな、と思いました。だから、インドで飲んだ紅茶を目指すということではなく、あくまで香り重視の日本の紅茶をつくろう、と。
それに、ゴールが決まっていると、小さくまとまってしまうことがある。今となっては、ゴールは具体的すぎない方がいいと思っています。方向性として「香り重視」とか、そのぐらいがいい。
秋林:確かに。同感です。では、後藤さんがお茶づくりで一番大切にしてることは?
後藤::どうやって邪魔しないようにできるか、というのが大きいです。原料に100%のポテンシャルがあったとして、邪魔しなければ100%が出せるはずなんですが、人が手を入れると落ちてしまう。そこを、できる限り損なわずに、葉の持つ力を最大限に引き出すにはどうしたらいいかを大事にしています。
そのために、製法の固定も理論化もしない。一般論としてはできますけど、天候などで環境が変わりますから、自然にそうなりますよね。毎回同じ環境になることはありえない。 その時その時のお茶の芽のポテンシャルを一番引き出せる製茶方法をとります。